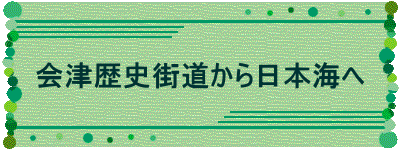第4章 吾妻渓谷・鬼押出し
第1部 吾妻渓谷と温泉
<温泉と食の計画>
新潟県長岡市から東京までは250kmの道のり。まっすぐ帰るのも芸がない。もう少し旅の余韻を楽しみたい。
「早く帰ってテレビでも見ながら明日への英気を養おう。」というご仁も世の中には多いし、そして確かにわたしもそう考えるときもあるのだが、貪欲にチャレンジするほうが好き。
昨夜から地図の上で赤鉛筆をもって旅行の行程に思案六法、思い悩んだ。考える上でのキーワードは「温泉」と「おいしいもの」の二つ。
1案は水上温泉に入浴後前橋インターで下り、蕎麦の名店「むそう庵」で昼食をとるコース。
第2案は赤城インターで下り、赤城山麓を回って宮城村柏倉の「喜楽庵」のこれも蕎麦コース、そして最終的に選んだのは、第3案の沼田で下りて「ロマンティック街道」を軽井沢まで下るコース。
<谷川岳>
 塩沢石打を過ぎ、越後湯沢のあたりから関越自動車道の前方に雪をかぶった谷川岳が見えてきた。
塩沢石打を過ぎ、越後湯沢のあたりから関越自動車道の前方に雪をかぶった谷川岳が見えてきた。このあたりは上越エリアのスキー場のメッカである。新幹線が整備され日帰りスキーができるようになった。上野から上越線で通った昔を思えば隔世の感がある。「越後中里」「石打丸山」「イワッパラ」「湯沢温泉」などのスキー場があった。
 川端康成の「雪国」の舞台も越後湯沢で、学生時代のスキー行には芸者・駒子を期待する何かがあった。
川端康成の「雪国」の舞台も越後湯沢で、学生時代のスキー行には芸者・駒子を期待する何かがあった。長い関越トンネルを抜けるとすぐに谷川岳パーキングが待っている。5月というのに残雪を抱いている。空の青さと山の緑とツツジのピンク、これだけでも素晴しいのに、おいしい空気のご馳走までついている。日本の自然の豊かさを改めて実感した。
<王 湯>
沼田で下りて「日本ロマンティック街道」を中之条に出る。
 ターゲットは吾妻渓谷「川原湯温泉・王湯」。
ターゲットは吾妻渓谷「川原湯温泉・王湯」。この温泉街はひなびた昔の雰囲気をそのまま残していて、わたしは好きだ。
川原湯温泉は800年ほど前に源頼朝が鷹狩りの際に発見したと伝えられ、王湯の壁には源氏の紋章の「ささりんどう」が刻んである。
湯かけ祭りで有名な古い温泉街の共同浴場。
 泉質は含食塩石膏硫化水素泉(79度)。渓谷の斜面に建てられているため内部が複雑になっている。階段を降りた脱衣場に衣類を脱いで露天風呂にはいる。「80度の源泉が出ています。水は細めにして、出しておいて下さい。」と注意書があった。
泉質は含食塩石膏硫化水素泉(79度)。渓谷の斜面に建てられているため内部が複雑になっている。階段を降りた脱衣場に衣類を脱いで露天風呂にはいる。「80度の源泉が出ています。水は細めにして、出しておいて下さい。」と注意書があった。かけ流しの湯はもったいないほどざぶざぶと使ってもすぐに溢れてしまう。新緑に囲まれた一人きりの露天風呂でゆったりした気分にひたる。
<美味・蕎麦の蒲焼>
 王湯の隣に小さな食堂がある。
王湯の隣に小さな食堂がある。時計はすでに午後の1時半。腹いっぱいいただいた出雲崎の朝食だが、そろそろお腹に隙間が出てきたので湯上がりに寄ってみた。
「もり蕎麦」のほかに「蕎麦がき」と、めずらしい「蕎麦の蒲焼」を頼んだ。
普通の小さな食堂なのに、ここの蕎麦は思いのほか美味しかった。群馬県の北部は蕎麦の名店が多いが、何気ない店で美味しい蕎麦に出会うと感激だ。もり蕎麦650円なり。
<水没?>

まったく残念で何とかならないかと思う。
ここは群馬県だから、田中長野県知事の思いも届かない。わたしもこの歳になって、理屈ではなく、自然の摂理を大事にしたいと思う気持ちが高まってきた。どんな理由があっても、大自然が、その生態系が工業の力で破壊されてしまうことの不条理には腹が立つ。
ここは「関東の耶馬溪」と歌われるほどの、紅葉と渓谷美の名勝地なのに・・・。
第2部 浅間山から軽井沢へ
<浅間山噴火>

| 1783年(天命3年)旧暦7月8日、前日からの鳴動は鳴り止まず、夜が明けても空一面黒煙に包まれ夜のように暗い。 午前11時、浅間山は光ったかと思う瞬間、大音響とともに真紅の火炎が数百メートルも天に吹き上げ、大量の火砕流が山腹を猛スピードで下った。土石は溶岩流に削り取られ土石なだれとして北へ流れ、家屋・人々・家畜などを飲み込みながら吾妻川に落ちた。たった十数分の短い出来事。鎌原村の被害は全18戸が流失、死者477人、死牛馬165頭、生存者はわずか93人のみという大災害に見舞われた。 この時代は近代的な経済政策を先取りした、世に言う「田沼時代」であったが、この大噴火と江戸の大火に加えて前代未聞の「天明の大飢饉」がおき、あえなく田沼意次は失脚した。 |
今でも溶岩流に埋まった村落の発掘の作業は続けられているという。
<鬼押出し>
 浅間山大噴火の溶岩の名残である。
浅間山大噴火の溶岩の名残である。「鬼押出し」の名は、火口で鬼が暴れ岩を押出したという、当時の人々が見た噴火の印象に由来する。その荒涼たる黒い岩の塊は末世を想像させる。
晴れていれば西側から四阿山(あずまやさん)、白根山、谷川連邦、男体山などが眺望できるのだが、この季節は春霞がすべての光景をだいなしにしてしまう。
<嬬恋村>
鬼押出しのある群馬県嬬恋高原といえば、山梨県の八ヶ岳山麓と同様に高原野菜の山地で、社会科の教科書にも収穫期の写真がよく掲載されている。特にキャベツは有名で、「玉菜(たまな)」と呼ばれている。秋口の首都圏のキャベツの供給はほとんどが嬬恋村のものだそうだ。品種改良の苦労の賜物で、みずみずしさの中に甘さを蓄えた逸品。感謝。
夏涼しく、冬雪の降る高原は観光開発にも絶好の立地条件を備えている。最近は軽井沢の向こうを張って「北軽井沢」の名称で別荘地開拓も熱心のようだ。西武グループがホテルやゴルフ場、レジャー施設を開発し付加価値の底上げを図っている。滞在型の観光には向いているのだろう。
アクセス的に少し遠いのが難点か。
<軽井沢白糸の滝>

道路わきの駐車場に車を止め、流れ下る沢に沿って200mほど緩やかに上ると、軽井沢の名勝「白糸の滝」が滝音も上品にわたしたちを迎えてくれた。
浅間山塊の水を集めて四季を通して豊かな水量を誇る。
一見何の変哲もない滝のように見える。しかし、小ぶりだが形のいい滝である。「軽井沢らしく品がいい」と表現してもいい。
ディティルを切り取ってみるとそのことがよくわかる。一つ一つが美しいのだ。いつまで眺めていても飽きない。
この日は観光客もほとんどいなかったせいもあり、滝音をBGMにじっくりと対話することができた。いい表情を見せてくれた。

<旧碓氷峠>
急ぐ旅でもなし、久しぶりに旧中山道を選んだ。七曲の峠道である。その昔、冬の峠はたいそう難儀であったが、今はトンネルを穿ち高速道路が走り、おまけにそれと平行して立派なバイパスまで開通した。したがって旧道を走る車はほとんどいない。よほどの物好きか暇人が走るぐらいで、すれ違う車も少ない。 おかげで面白いものを見てしまった。猿の群れだ。通る車も少ないからだろうが、猿軍団はわがもの顔で道路を占領していた。数十匹の猿の群れが道路の左右に、あるいは石垣の上下に群れている。まるで猿の惑星にタイムスリップしてしまったかのようだ。
おかげで面白いものを見てしまった。猿の群れだ。通る車も少ないからだろうが、猿軍団はわがもの顔で道路を占領していた。数十匹の猿の群れが道路の左右に、あるいは石垣の上下に群れている。まるで猿の惑星にタイムスリップしてしまったかのようだ。松井田インターから関越に乗って、「歴史街道を巡る」長い旅は幕を閉じた。
<完>
第1章 | 第2章 | 第3章 | 第4章
Copyright ©2003-6 Skipio all rights reserved